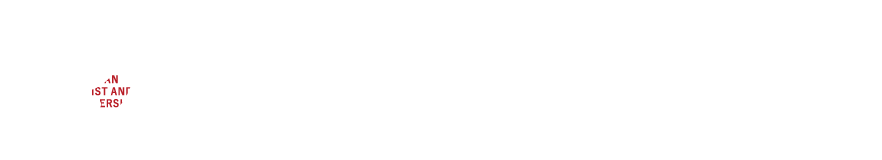コラム
柔道整復師に向いてる人の特徴とは?性格・スキル・やりがいまで徹底解説
2025.7.18

柔道整復師に向いてる人の特徴とは?性格・スキル・やりがいまで徹底解説
柔道整復師という職業に興味があるけれど、自分に向いているのかどうか不安に感じていませんか?
この記事では、「柔道整復師に向いている人の特徴」や「必要なスキル」などをわかりやすくまとめました。
これから柔道整復師を目指す方や、進路に迷っている方にとってヒントとなる情報をたっぷり詰め込んでいますので、ぜひ最後までご覧ください。
柔道整復師に向いてる人の特徴とは?

このセクションでは、柔道整復師に向いているとされる人の「特徴」を紹介します。好きなことや関心が仕事にどう活きるのかを見ていきましょう。
人と接するのが好き
柔道整復師は患者さんと毎日接する仕事です。
人とのコミュニケーションが好きな人にとって、非常にやりがいを感じやすい職業です。
施術中に会話をしながら安心感を与えることが求められるため、話すことが得意な人は強みになります。
また、信頼関係を築けることで患者さんが継続して通院しやすくなるなど、好影響がたくさんあります。
体や運動に関する興味がある
柔道整復師の仕事は「骨格」や「筋肉」、「関節の動き」などを理解して対応するものです。
運動やスポーツが好きで体の構造に興味がある人は、知識の習得もスムーズでしょう。
スポーツトレーナーとしての道も広がるので、将来的にスポーツ選手をサポートしたいという夢がある人にも向いています。
学びが仕事に直結するため、知識欲のある人にもおすすめです。
困っている人を助けたいという気持ちが強い
「誰かの役に立ちたい」「困っている人を支えたい」という想いは、柔道整復師の原動力になります。
ケガや痛みで困っている患者さんに対し、直接手を使ってサポートできるのがこの仕事の魅力です。
回復して笑顔になる姿を見ると、大きなやりがいを感じられます。
優しさや思いやりの気持ちが強い人ほど、長く活躍できる職業です。
柔道整復師に向いてる人に多い性格や考え方
向いている人の「性格」や「考え方」に注目すると、自分の特性と照らし合わせやすくなります。
コミュニケーションを大切にする性格
柔道整復師は患者さんとの信頼関係がとても大切です。
相手の気持ちに寄り添って話ができる人は、施術の効果も高まりやすくなります。
「ただの会話」ではなく「安心感を与える会話」が求められるため、聞き上手であることも大きな強みです。
人と関わる中でエネルギーをもらえるタイプの人は、この仕事に向いています。
細かい作業が苦にならない性格
手技による施術では、細かな力加減や動きが必要です。
そのため、コツコツとした作業が得意な人や集中力のある人が適しています。
一つ一つの動作に丁寧さが求められるため、雑な性格よりも几帳面な人の方が適性があります。
施術の質を上げるためには、毎日の積み重ねが欠かせません。
相手の立場で物事を考えられる
患者さんは不安を抱えて施術を受けに来ます。
そのため、相手の気持ちを想像して対応できる人は、安心感を与えやすくなります。
「どうしたら痛みを軽くできるか」「どんな言葉をかければ安心するか」といった視点が大切です。
共感力の高い人は、柔道整復師にとても向いています。
柔道整復師に向いてる人が持っているスキルや能力

柔道整復師に向いている人は、特定のスキルや能力にも優れています。以下で詳しく見てみましょう。
正しい姿勢や骨格の知識を持っている
体の構造に関する基本的な知識は、柔道整復師に欠かせません。
姿勢や骨格に詳しい人は、施術のポイントを正確に捉えることができます。
スポーツ経験がある人は自然とこれらの知識を持っていることが多いため、非常に有利です。
理解が深まると、患者への説明やアドバイスにも説得力が増します。
手技の習得に集中できる器用さがある
柔道整復師の基本は手技による施術です。
手先が器用で細かい作業に集中できる人は、技術の習得が早く上達も早い傾向にあります。
また、患者の状態に応じて技をアレンジできる柔軟性も重要です。
実践と練習を積み重ねながらスキルを高めていく姿勢が求められます。
説明力やカウンセリング力がある
施術だけでなく、患者さんへの説明やアドバイスも大切な仕事の一部です。
痛みの原因や今後のケア方法をわかりやすく伝えられる力は信頼関係を築く上で欠かせません。
聞き手の理解度に合わせて話せる人は、それだけで安心感を与えることができます。
言葉によるサポートも、柔道整復師の重要な役割です。
柔道整復師に向いてる人と向いていない人の違い
ここでは、柔道整復師に向いている人と向いていない人の違いについて解説します。
体力や持久力に差がある
柔道整復師の仕事は立ち仕事が多く、体力や持久力が必要です。
一日中動き回ることもあるため、体を使う仕事に慣れていないときつく感じるかもしれません。
逆に、普段から体を動かすのが好きな人やスタミナに自信がある人には向いています。
疲れていても笑顔で接する力も求められます。
人と関わることが好きかどうかの違いがある
柔道整復師は人と関わる時間が非常に長い仕事です。
人との関わりにストレスを感じやすい人には負担になるかもしれません。
逆に、人の話を聞いたり、気遣いができる人は大きな強みになります。
性格の面でも向き不向きがはっきり出る部分です。
向上心があるかないかで差が出る
医療やリハビリの分野は日々進化しています。
学び続ける意欲=向上心がある人は、自然とスキルが上がり、結果として多くの患者に貢献できます。
逆に、現状に満足して学ばなくなると、施術の質が落ちてしまう可能性があります。
成長意欲の有無が、キャリアに大きな差を生むのです。
柔道整復師に向く人になるために意識したいポイント
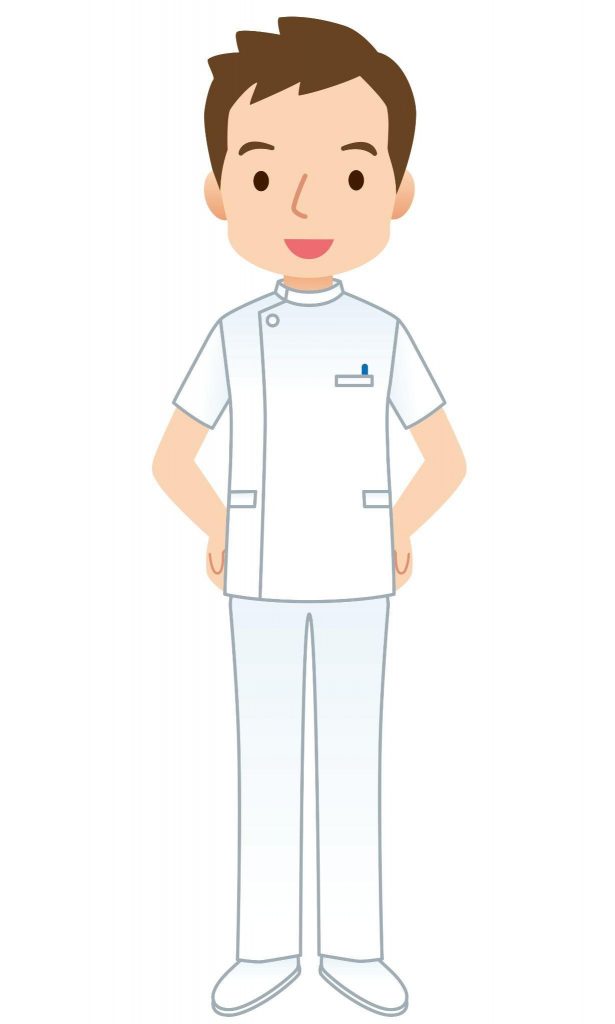
ここでは、柔道整復師に向く人になるために意識すべきポイントを紹介します。今からでもできる行動がたくさんあります。
患者との信頼関係を築く意識を持つことが大切
技術だけではなく、「この先生なら安心できる」と思ってもらうことが非常に重要です。
そのためには、日々のコミュニケーションや対応の一つひとつに丁寧さが求められます。
患者さんの立場になって考えることで、信頼される柔道整復師に近づけます。
目の前の人を大切にする気持ちが、結果として評価につながります。
日々の勉強と技術のアップデートが必要
柔道整復の知識や技術は、日々進化しています。
学び続ける姿勢がないと、時代に取り残されてしまいます。
勉強が苦手でも、興味があれば自然と知識は身についていくものです。
セミナーや研修に積極的に参加することも、スキルアップにつながります。
チーム医療や他職種連携を理解しておくことが重要
近年、医療や福祉の現場では「チーム医療」が重要視されています。
柔道整復師も他の医療職や福祉職と連携しながら患者をサポートすることが増えています。
そのため、他職種とのコミュニケーションや役割理解も必要です。
柔道整復師は単独で完結する職業ではなく、協調性も求められる仕事です。
柔道整復師に向いてる人が感じるやりがいとは?
柔道整復師として働く中で得られる「やりがい」はたくさんあります。以下でその一部を紹介します。
患者の痛みを和らげて感謝される喜びがある
何よりも大きなやりがいは、「ありがとう」の言葉を直接もらえることです。
痛みを抱えていた患者さんが元気になり、笑顔で帰っていく姿を見ると心から嬉しくなります。
「この仕事を選んでよかった」と実感する瞬間が何度も訪れるでしょう。
直接人の役に立つ仕事だからこそ、喜びも大きくなります。
スポーツ選手の回復を支えられる達成感がある
柔道整復師の中には、スポーツ現場で活躍する人も多くいます。
ケガをした選手が試合に復帰できたときの喜びは格別です。パフォーマンス向上に貢献できたときの達成感も、大きなモチベーションとなります。
スポーツ好きな人にとっては、やりがいが何倍にも感じられるでしょう。
地域の健康を支える存在になれる
柔道整復師は地域密着型の医療職でもあります。
高齢者や働き盛りの方など、幅広い世代の健康を支える存在です。
「この町にあなたがいてくれてよかった」と言われるような信頼を築くことができます。
地域社会に貢献したい人には、ぴったりの仕事です。
まとめ|柔道整復師に向いてる人の特徴を知って将来を考えよう
今回は、柔道整復師に向いている人の特徴や性格、必要なスキル、やりがいについて詳しく解説しました。
人と関わることが好きな人、体や運動に興味がある人、困っている人を助けたいという気持ちが強い人は、この職業に非常に適しています。
また、勉強やスキルアップに前向きであれば、年齢や経験に関係なく目指せる職業でもあります。
将来の進路に悩んでいる方は、自分の性格や考え方を見つめ直し、「柔道整復師」という選択肢を一度検討してみてはいかがでしょうか。
あなたのやさしさと努力が、誰かの健康と笑顔を支える力になります。
【接骨院・整骨院の開業は、ジャパン柔道整復師会にお任せください】
今回この記事を読んで、整骨院の開業を本格的に検討し始めた方もいらっしゃるかと思います。
整骨院の開業は、ぜひジャパン柔道整復師会にお任せください。
ジャパン柔道整復師会では、接骨院・整骨院の開業を全面的にサポートしております。
- 事業計画の作成
- 開業場所の選定
- 商圏調査
- 物件の紹介
- 融資の資料作成
- 届出の書類準備
- 治療機器の販売
- ホームページの作成
といったように単なるアドバイスにとどまらず、実際に手を動かし開業準備を進めます。
詳しいご支援内容は以下の記事をご覧ください。
仕事をしている間も私たちが着々と準備を進めますので、今の仕事を続けながら開業の準備が整います。中には開業の前日まで、仕事を続けていた方もいらっしゃいます。